最初に山谷が交通の結節点に挟まれているという地理的条件に触れました。交通というのは共同体から外部へ出ていくことですから、その要衝というのは周辺部に発達します。
そうした周辺部には中心から遠ざけられたものが置かれ、それがたとえば処刑場や遊郭だったわけです。それらは最初、江戸がまだ小さい段階では日本橋付近にありましたが、都市の膨張にともなって、だんだん千住界隈などへと移動してきた、その流れをこれまでみてきました。
さて、同じように都市周辺部に発達し、現在の山谷に直接つらなるもの、山谷の発展の核になったものが木賃宿(きちんやど、ぐれやど)だったと考えられます。山谷は、江戸時代からすでに旅館が軒を連ねる町だったのです。その面影は現在も感じとれるのではないでしょうか。
以下ではまず木賃宿について触れ、それが少しずつニュアンスを変えていく過程を追いかけてみたいと思います。

 木賃宿というのは江戸時代、街道筋のはずれにはよくあった最下層の旅館のことをいいます。今でいう簡易宿泊所のようなもので、自炊を基本とし、自炊のための薪程度の料金で泊まれたそうです。 木賃宿というのは江戸時代、街道筋のはずれにはよくあった最下層の旅館のことをいいます。今でいう簡易宿泊所のようなもので、自炊を基本とし、自炊のための薪程度の料金で泊まれたそうです。
深井甚三「江戸の宿」(平凡社新書)によれば、十返舎一九が「東海道中膝栗毛」で木賃宿の様子を描いていて、その描写は広重の描く版画にも対応し、信頼度が高いそうです。深井氏の要約を借りると以下のような感じらしい。
『まず、その場所は宿場のはずれに位置し、家内の広さは四、五畳の板敷きで、仏壇と破れつづらのほかは何もなく、いろりがもうけられているだけであった。泊まり客は六部と巡礼親子という設定であるが、彼らは米を出し合って、宿の老婆にいろりの鍋で粥を煮てもらうが、米も弥次・喜多はただみているだけであった。
就寝は、寝ござと薄い布団を使うだけですまし、蚊帳などもないので、六部は蚊よけに笈に入れていた紙の蚊帳をかぶり、みないろりの周りで寝るものであった。ただ、娘と宿の老婆は、男どもとは別に、梯子をかけて天井裏を利用する話となっている』
ここで宿泊客は「六部と巡礼親子」となっていますが、六部というのもようするに巡礼者のことです。木賃宿は巡礼客によってよく利用されたようです。
ところが、注意しておきたいのは巡礼者というのは聖なるものであると同時に、そもそも自由な移動が必ずしも簡単ではなかった時代には非日常的な遠い存在で、また、しばしば“ワケアリ”のひとが巡礼を装ったりして、そのため巡礼客がイコール素性の知れない怪しい存在とみなされることも少なくなかったということです。
だから、そうやって巡礼客の利用頻度が増えていくと今度は一般の客が遠のいていき、だんだん木賃宿は「最下層の旅館」となっていくという理屈があったらしいのです。
さらにいえば、その下層の旅びとに帰る場所が必ずあるとは限りません。むしろ帰る場所がないからこそ漂泊しているということもあるでしょう。そうすると、木賃宿が一時的な宿泊所というよりは日常的、持続的な住居代わりとなって、そこが終の棲家になるといったことも起こってきます。
そして明治時代に入ってなお、江戸・大坂などの大都市近郊では独身者の貧窮したひとびとの住まいとして木賃宿は利用されていたといいます。
山谷の原点は江戸時代にあり、といったところでしょうか。
しかし、いくつかの要素がまだ欠けています。
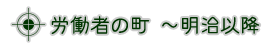
簡単に調べた限りでは、明治から戦後まで、山谷の姿はおぼろげにしか歴史に登場してきません。
その間、おそらく山谷は、すでに触れたように木賃宿のたち並ぶ小さな町でありつづけたわけですが、それを取り巻く環境は大きく変わってきます。
明治以降、中央集権的な産業発展が始まるからです。
 同じ台東区にある上野は、今日そうであるように、地方から上京してくるひとびとの玄関口でした。しかし、それは単なる宿場という以上に、東京を中心に整備された鉄道網をつうじて地方の疲弊した農村から労働力を掻き集め、富と力とを増強しようという国策のなかでは別の意味をもつようになったと考えられます。つまり、上野は旅びとにとっての玄関という以上に労働予備軍にとっての玄関となるわけです。
同じ台東区にある上野は、今日そうであるように、地方から上京してくるひとびとの玄関口でした。しかし、それは単なる宿場という以上に、東京を中心に整備された鉄道網をつうじて地方の疲弊した農村から労働力を掻き集め、富と力とを増強しようという国策のなかでは別の意味をもつようになったと考えられます。つまり、上野は旅びとにとっての玄関という以上に労働予備軍にとっての玄関となるわけです。
その上野では、あてもなく着のみ着のまま働き口を求めて東京にやってきて、そのまま野宿する光景が多く見られたそうです。これは、かつてのよるべなき漂泊の民とはずいぶん意味あいが違うでしょう。
江戸時代の漂泊には、多少誇張をまじえて言えば、牧歌的な静けさがあったと想像されます。ところが、労働しなければ生きていけない時代が到来し、競って就労を求めるにもかかわらず、それが叶わず野宿するしかないとすれば、そこにはかつてない切迫感があるのではないでしょうか。そしてこれは産業社会に特有なものと思われます。
そうした上野の周辺に、上野では吸収しきれないひとびとの受け皿として、同様の町形成が起こってきます。そのひとつが山谷でした。
それから関東大震災によって江戸の面影の多くが失われ、さらに空襲によって東京は焼き払われました。こうして断続的な破壊が繰り返されるなかで、東京都下、とくに上野周辺には多くの被災者が集まってきたといいます。震災のときも空襲のときも。
それが問題化され、山谷と関係してくるのが戦後の話になります。

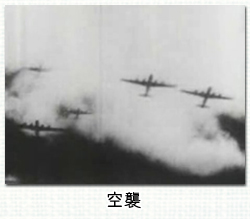 戦後のGHQ(占領軍)による統治時代、突如として山谷がクローズアップされます。 戦後のGHQ(占領軍)による統治時代、突如として山谷がクローズアップされます。
というのも、GHQが上野に集まった被災者たちを様々な理由で恐れたからです。群衆心理を思い起こせば一番わかりやすいと思うのですが、ひとつの場所に不満をもった人間が多く集まるのは統治機構にとっては危惧されることです。また、疫病の流行なども考えられます。
そこでGHQは上野の被災者たちを各地に散らして治安を維持しようとし、東京都はGHQの指導のもと、首都周辺にテント村(仮設の宿泊施設)を建設します。その拠点のひとつが浅草山谷だったのです。
ちなみにいうと、その他にテント村がつくられたのは、旭町、大木戸、緑町、深川、品川、厩橋でした。(前掲「現代棄民考」)
隅田川沿いは一面焼け野原になったそうです。ご老人たちの記憶を尋ねると多少の食い違いがあるのですが、山谷は完全には焼かれなかったらしく、それで民間の旅館組合などが余力を残していたのでしょう。それが東京都の委託を受けて、テント村建設の主体になっていきます。
これこそ現在につながる山谷の原型となります。
 以上のように、山谷は最初は旅びとのための木賃宿が立ち並ぶ町でしたが、徐々に下層民の滞留する場所へと変貌し、やがて労働者のための町へ、さらには戦争被災民を受け容れる場所として使われるようになります。
以上のように、山谷は最初は旅びとのための木賃宿が立ち並ぶ町でしたが、徐々に下層民の滞留する場所へと変貌し、やがて労働者のための町へ、さらには戦争被災民を受け容れる場所として使われるようになります。
また、角度を変えて捉え返すと、最初は自然発生的な町だったわけですが、戦後になると統治機構の主導のもと、もっとも悲惨なひとびとの受け皿として人為的に形成されたという側面が濃厚に出てきます。
その後、復興がすすむにつれ、山谷のテント村に集まった、集められたひとびとはそれぞれの元いた場所へ帰っていったといいます。
そしてテント村は改装され、木造建築の宿泊施設が林立する現代の山谷がまさにそこで始まりました。
しかし、彼らは本当に自分の住むべき場所へ帰れたのでしょうか?
これがそのつぎの物語となります。
|