ここでは終戦直後から高度成長前夜までの流れを考えていきます。
あらためて確認すると、行政は戦後の焼け野原をまえにして、テント村を設営し、被災者たちに仮の住まいを与えました。その背景には一面でヒューマニズムの思想があったのはたしかでしょう。ところが、同時にそれが「治安維持」のための処置という側面を併せ持っていた点には留意すべきかと思われます。
以下では少し文章のトーンを変えて、また、前掲「現代棄民考」などを参考にしながら、その当時、そしてもしかすると現在にいたるまで、山谷やその周辺をめぐって作用した/している権力のはたらきについて注目してみようと思います。

まず、被災者というのは多くの場合に不満にみちたひとびとだということを想起しておく必要があるように思えます。被災体験はそれ自体で不条理ですが、不条理感は往々にして怒りに変わります。そしてそうした怒れる人々が数多くいた場合、それは秩序の側にとって「危険」極まりないことでした。
また、どういうひとたちが被災者になりやすかったかといえば、それは社会のなかで不利な立場に置かれているひとたちでした。そこには被差別部落や在日朝鮮人の方々が少なからず含まれていたでしょう。
ただし、実際にどれだけの人数が含まれていたかは不明です。ですが、ここでは人数は問題ではありません。それよりも、秩序の側からみて、それまで差別的に扱ってきた相手が被災者のなかに数多く含まれている可能性、事実というよりその可能性があるということこそが、被災者たち、つまり住み処をなくして彷徨っているひとびとに対する「恐れ」を煽り立てたであろう。そして、それまでの差別的待遇に対する後ろめたさの裏返しとしての「恐れ」を強めたであろう、そうした前後関係が大事に思えます。

 こうしてまさに「治安維持」のためにテント村が建設され、やがて日本の復興がすすんだという理由で解散されたのは前述のとおりです。ですが、そもそも数ヶ所のテント村だけであれだけの人数の被災者たちを収容できたのでしょうか。また、運よくテント村に入れた被災者たちは、テント村が解散されたあと帰るべき場所に帰れたのでしょうか? こうしてまさに「治安維持」のためにテント村が建設され、やがて日本の復興がすすんだという理由で解散されたのは前述のとおりです。ですが、そもそも数ヶ所のテント村だけであれだけの人数の被災者たちを収容できたのでしょうか。また、運よくテント村に入れた被災者たちは、テント村が解散されたあと帰るべき場所に帰れたのでしょうか?
結論からいうと、やや強い調子でいえば「テント村は焼け石に水だった」という表現もできるかもしれません。つまり、そもそもテント村に収容されずに路頭に迷ったままのひとびとはまだまだ数多くいたということです。
そしてテント村にしても、そこが木造の宿泊所に改装されたあと、一部のひとびとはそのまま居残って、のちに日雇い労働者になったと考えられます。また、なんらかの理由で宿泊施設を離れ、そのまま何もせず、あるいは出来ず、路上生活に入っていったひとびとも少なからずいたと考えられます。つまり、帰れなかったひとびとはたくさんいただろうということです。
たしかに個々の事例は多様で一概には言えません。また、帰るべき場所に帰れた人々がいたのは疑いえません。しかし、戦争によって家や財産を失って貧困に転落したり、最初から貧困にあえいでいた者がさらなる貧困に陥ったり、その過程で心身を病んでどん底から這い上がれなくなったり、さらには他人には言えないなんらかの理由でそうした一群のひとびとに混じって生活したりするなど、様々なケースが考えられます。
ともあれ「帰る」ということは、精神的・肉体的に、あるいは経済的な理由などからして、そんなに簡単な話ではないわけです。
そうすると、テント村の解散がイコール平穏な生活への復帰を意味しなかったケースは多々あったでしょう。むしろ、新たな困難の始まりだったとさえいえるかもしれません。
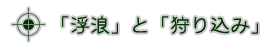
これらの帰れないひとびとは当時「浮浪」と呼ばれました。
ここに戦争被災者たちが含まれていたのは述べてきたとおりですが、そのうえに部落・在日・貧困・病気・障害…などなどに対する差別意識が重ねられ、さらには秩序にとっての不穏分子である、もしくはそうかもしれないという理由から、彼らはじつに不当な扱いをうけることになります。
今日からみてグロテスクさで際立っていたのが「狩り込み」と呼ばれる行為でした。これは、警察官などが浮浪者をしらみ潰しに探し出し、見つけ次第、彼らを公園や公道から排除する作業をいいます。ようは「浮浪者狩り」です。
警察官が「おぃおぃ、ここは寝る場所じゃないぞ」と声をかける風景は今日でもよくみられますが、それがエスカレートしてホースで水をかけるようになるとニュアンスはかなり違ってきます。とくに冬場にそれをやられたら命にかかわることだってあります。水をかけるほうは「殺してない」つもりでも、やられるほうの肉感的な恐怖は想像して余りあります。
さらに「狩り込み」が行政的に組織化された場合には、ターゲットは個々の浮浪者というよりも、地域そのもの、環境そのものとなっていきます。当時、さかんに「環境浄化」ということが言われましたが、それは、一般市民にとっての「暮らしやすい綺麗な街づくり」と同時に「浮浪者のいない街づくり」を意味していました。
権力にとっては、「治安維持」のためにテント村を建設するのも「環境浄化」のために浮浪者を排除するのも、ようするに同じことなのかもしれません。秩序が維持され、国がより豊かになり、また強くなればいいわけですから。
そして、そうした発想を一般市民も共有していればこそ「浮浪者のいない街づくり」は説得力をもち、市民がみずから浮浪者に石を投げるということが起こったのではないでしょうか。
今日からみると社会福祉的なセンスとはあまりに正反対の対応に驚かされますが、なにしろ日本において福祉の諸制度が本格的に整備されるのは戦後になってからですので、この時期にそれを期待するのはムリというべきでしょうか。それにしても、意識の低さは覆うべくもありません。むしろ逆に、この「狩り込み」と「環境浄化」とは、高度成長期を代表する国家的イベントたる東京オリンピックにむけてさらに加速していきます。
戦後日本が少しずつ輝きだす頃、それとは逆の薄暗い排除が進行していたとも言えそうです。

しかし帰れないひとびとにも日々の生活はあるわけです。
 ですから、たとえば廃品回収などをしながらその日の糧を手に入れ暮らしを成り立たせていた例などは少なくありません。また、そのさい集落を形成し、相互扶助によって生存を成り立たせた例もありました。
ですから、たとえば廃品回収などをしながらその日の糧を手に入れ暮らしを成り立たせていた例などは少なくありません。また、そのさい集落を形成し、相互扶助によって生存を成り立たせた例もありました。
「浮浪者」や「路上生活者」というとバラバラな砂のように互いに無関心というイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうではなく、人間は助け合わねば生きていけないということの原点を感じさせる例もあったわけです。
 他方、「狩り込み」という行為の頂点には、上記のような浮浪の集落を火で「焼き討ち」するなどといったことがあったといいます。今日からすると俄かには信じがたいのですが、この「焼き討ち」とともに「相互扶助」の事実をよく伝えてくれるのが「蟻の街のマリア」の物語です。 他方、「狩り込み」という行為の頂点には、上記のような浮浪の集落を火で「焼き討ち」するなどといったことがあったといいます。今日からすると俄かには信じがたいのですが、この「焼き討ち」とともに「相互扶助」の事実をよく伝えてくれるのが「蟻の街のマリア」の物語です。
よく知られたように、「蟻の街のマリア」はフィクションではなくてノンフィクションです。これは「狭義の山谷」が舞台ではありませんが、今の浅草公園あたりが舞台なので「広義の山谷エリア」での出来事とは言えます。
当時「バタヤ」と呼ばれた廃品回収業者たちの集落「蟻の街」は、何人かの有能なオルガナイザーや宣教師の努力が不可欠だったとはいえ、ほぼ自然発生的に形成されたものかと思われます。そこに北原怜子という女性が入っていき、溶け込み、やがて「蟻の街のマリア」と呼ばれるようになります。
この物語で大事なのは彼女の苦悩の深さという点だろうとは思うのですが、ここでは措き、注目してみたいのは以下の点です。
つまりこの物語の終盤、「蟻の街」のひとびとは各地での「焼き討ち」のニュースを聞きながら、立ち退き勧告をうけるわけです。
しかしながら、彼らは、こここそが自分たちの生きる場所なんだということを粘り強く訴え、それまで一切の交渉を拒否していた行政側を交渉のテーブルにつかせることに成功します。そして、最終的には代用地への移転が決まるわけです。
実際には、もともと「蟻の街」があった場所から引き剥がされてしまったという意味で、また、移転先が現在の「夢の島」の近隣という意味でも、さらに重要なのは移転のための重すぎる費用を負担しなければならないという条件を呑まされたという意味でも、それは傷だらけの撤退戦をひたすら後退した、逃げ切ったとすら言えない後味の悪い結末だったと思えます。
ただ、「狩り込み」に代表され「焼き討ち」を頂点とする権力の圧力に対して、バラバラのままだったひとびとは抵抗すら出来ず、また、集落としてまとまったひとびとの多く内外の圧力によって分裂せざるを得なかったといいます。その点において、前傾「現代棄民考」は「蟻の街」の事例を稀有だったと位置づけています。


 そして、山谷の歴史がさらに高度成長期へと続いていくなかで、そこでは「マリア」の交渉と祈りによる非暴力的で静かないき方とは対照的な、政治的で暴力的な「山谷暴動」が一個のクライマックスとなっていきます。 そして、山谷の歴史がさらに高度成長期へと続いていくなかで、そこでは「マリア」の交渉と祈りによる非暴力的で静かないき方とは対照的な、政治的で暴力的な「山谷暴動」が一個のクライマックスとなっていきます。
次回はその山谷暴動について触れていきます。
なお、最後に一言だけ補足しておくと、現在でも新宿地下街のホームレスを強制排除するといったことが時折あって、それをわたしたちはともすると仕方がないことと感じているかもしれません。しかし、そうした強制排除のルーツこそ、これら「狩り込み」であり放水であり、そして「焼き討ち」だったということも事実かと思われます。
|