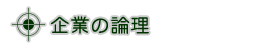
前掲のファウラーはこう書いています。
これら総合建設産業の成功は皮肉なことに、多くの労働者をいかに雇用せずにすませられるかという能力に大きくかかっている。そのために子会社、孫会社、現場監督、手配師を通じて最後には山谷のような寄せ場に至るネットワークで仕事を手配する複雑な子会社制度が使われる。…幾僧にも重なったこの制度は、とくに景気の変動が極端な建設業界で大手企業に緩衝装置を提供する。底辺の男たちはもっとも景気がいい時期以外は、仕事数は最低で、寄せ場ではいつでも典型的に50パーセント以上の失業率に甘んじるしかない。
ここでひとつの見取り図を示しておきたいと思います。
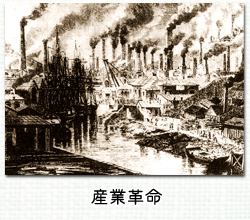 まず、資本制という社会経済システムは、欲望を自由に追求すべしという原則のもとで発達してきました。その「自由」のうちには企業による「首切り=リストラの自由」が含まれ、その点ではファウラーがいうゼネコンの「いかに雇用せずにおくか」という能力は、資本制下の企業にとってはごく当たり前のこととも言えます。 まず、資本制という社会経済システムは、欲望を自由に追求すべしという原則のもとで発達してきました。その「自由」のうちには企業による「首切り=リストラの自由」が含まれ、その点ではファウラーがいうゼネコンの「いかに雇用せずにおくか」という能力は、資本制下の企業にとってはごく当たり前のこととも言えます。
ただ、初期の資本制が「自由」を荒々しく行使したがために労働者が激しく窮乏化し、かえって社会は不安定になってしまいました。そこから労働運動が生まれ革命闘争が生じたわけですが、やがて国家が生存権を保障し企業が雇用を保障するというかたちで秩序の安定が図られ、こうして成立していくのが福祉国家という段階でした。
初期の資本制が「切り捨て」を基本モードとしていたとすれば、福祉国家は逆に「包摂」を機軸としていると言っていいでしょう。
これを補助線にすると戦後日本と山谷の特殊な関係があらわになります。
まず、戦後の日本社会には終身雇用制という極めて安定した労使関係を構築していくという流れがあるわけですが、西欧の福祉国家とは異質と言われるにせよ、これも「包摂」のひとつのありようとは言えます。
他方、戦後日本は驚異的な経済成長を実現しますが、その推進力になったのがゼネコンであり、ファウラーも同書で言うように、全企業に占めるゼネコンの比率の高さは戦後日本に特徴的でした。そのゼネコンを中心に形成された経済成長システムの末端に位置するのが日雇い労働者たちの寄せ場であり、そこではまさに「切り捨て」のモードが作動します。
つまり、戦後の日本社会は人口の大部分を占める中流層と下層とで二重構造になっていて、その下層に対しては荒々しい「切り捨て」が行われたということです。
そのゼネコンにはどういう特徴があったでしょうか。
建設業というのは他の業種と違って一個の建築物が完成すればその労働者は不要になります。はっきり言えば建設業者にとって労働者を常時雇用しておくのは不利益以外の何者でもない、少なくともその傾向が格段に濃厚なのが建設業と言えます。
もちろん建設は何度も繰り返されるのでたえず労働者は必要なのですが、必要なのはイキのいい若い労働者であって、老いた熟練の労働者はそれほど多くは要りません。むしろ、新しい血液をつぎつぎ導入でき、要らなくなったら使い捨てにできるシステムこそが建設業にとっては最適です。
だから、ゼネコンは日雇い労働者を絶対に「包摂」しようとはしません。端的に労働者の生活のことは知らない、保障しようとしない。そうやって包摂せず排除したまま、しかも一回の切り捨てには終わらず、利用するだけ利用しようとする、これがファウラーの言う「いかに雇用せずにおくか」ということの真の意味でしょう。
つまり、いつでも切り捨てられる労働力(労働者でなく労働力)のプールとして、寄せ場は企業の論理、ゼネコンの論理によって必要とされているわけです。
そのゼネコンが牽引しながら戦後の高度成長とその成果としての「豊かさ」が実現したとすれば、中流層の「包摂」―それは豊かさの証と言えるでしょう―というのは切り捨てられた彼らを捨て石にしてこそ可能となった、あるいは控えめに言ってもそうした一面があったとは言えるのではないでしょうか。
社会全体が「包摂」へと向かおうとしている時代にあってそうした包摂されざる者が必要とされた、そのコントラストこそ、山谷の悲惨の一端を示しているように思えます。

ところで、日雇い労働者そのものは実は近代以前から存在していました。城の改築や河川事業のため、短期で人夫を徴用し、金銭で支払っていたわけです。
ただ、そうした仕事に従事したのは農民や町人ではなく、既存の生活秩序からはあぶれた者たちでした。あぶれ者たちが日銭を稼ぐために日雇い労働に携わったのです。
 また、江戸期の市政はそうした労働力をつねに一定多数プールしておくため、彼らが住まう場所を指定し管理して、そうした場所に任侠の人々、いわゆるヤクザ者が巣食い、場所を仕切ったりするのを黙認したりしていたそうです。 また、江戸期の市政はそうした労働力をつねに一定多数プールしておくため、彼らが住まう場所を指定し管理して、そうした場所に任侠の人々、いわゆるヤクザ者が巣食い、場所を仕切ったりするのを黙認したりしていたそうです。
これを人足寄せ場、人足制と言います。
この意味で山谷のような寄せ場には歴史的伝統があり、いつの時代にもあったものと見ることもできます。実際、ファウラーはそのように記述しています。
しかし、かつて悪所と呼ばれ漂泊の民の町だった山谷が日雇い労働者の町に変貌していくのは明治以降であって、「純粋な」寄せ場に変貌するのは戦後のこと、とくに高度成長の時代以降です。
したがって、山谷という場所の独自のニュアンスを言うためにはもう少し補足が必要に思えます。
それは一言でいえばこういうことではないでしょうか。
つまり、寄せ場の役割や機能が違っているのです。
かつての人足制は必ずしも「成長」を下支えするものではなく、秩序からはみ出した者たちを再び秩序のなかに組み込み、権力のために有効活用することだけを目的にしていたように見えます。近代の山谷、もしくは近代の寄せ場一般にもたしかに同じようなところはあります。
 ですが、寄せ場から引き出されるもの、その量、大きさ、成果が違っているように思えます。かつては城や防波堤などのインフラストラクチャーだけが作り出されましたが、それは既存の秩序に変更を命じない、いわばメンテナンスと言えます。ところが、それに対して高度成長期には、たとえば東京タワーの建造が呼び水となって「成長時代」そのものが創出されていきます。このとき構造物の生産は、決して一回的なものではなくて、それを誘因とするさらなる生産を目指しています。だからこそ「成長」していくわけです。いわば、ここでは社会がトランスフォームしていくのです。 ですが、寄せ場から引き出されるもの、その量、大きさ、成果が違っているように思えます。かつては城や防波堤などのインフラストラクチャーだけが作り出されましたが、それは既存の秩序に変更を命じない、いわばメンテナンスと言えます。ところが、それに対して高度成長期には、たとえば東京タワーの建造が呼び水となって「成長時代」そのものが創出されていきます。このとき構造物の生産は、決して一回的なものではなくて、それを誘因とするさらなる生産を目指しています。だからこそ「成長」していくわけです。いわば、ここでは社会がトランスフォームしていくのです。
そうした高度成長の頂点に「列島改造」(1972年)が出てくるというのが戦後史の一断面と言えるのではないでしょうか。
寄せ場の役割や機能が前近代とは違っているというのはこの意味においてです。
日雇い労働者たちの労働は、こうして戦後社会に貢献しながら貢献した瞬間に忘れられていくという位置にありました。

ここで、前近代的な人足寄せ場を今日でいうヤクザが仕切っていたことを思い出しておきましょう。
日雇い労働というのはいわゆる3K労働で、多くの人はやりたがらないわけです。そういう労働をゼネコンなり国家的戦略としての高度成長なりが必要としたらどうなるでしょうか。やりたくないものをやらせるわけですから、時にそれは「半強制」的な色彩を帯びることがありえます。
そして、企業が手を染めたがらないそうしたダーティ・ワークを誰が代理し労働力を手配するかといえば、ここに暴力団が介在してくる余地が生まれるわけです。
 被災や貧困や病気のため、働き口がない者が路頭に迷っているときに誰かが肩を叩きます。そのとき、その人が最低限の食事や住まいを用意してくれると囁いたらついていく者もあるでしょう。しかし、どんなに働いても自立できるだけの対価を与えられないとすれば、その生活はやがて泥沼にはまっていき、いわゆるタコ部屋生活に行き着きます。「まるで強制収容所のよう」と形容されるのがタコ部屋です。それを警察や行政が黙認していれば、そこから逃れる手段は路上生活しかありません。 被災や貧困や病気のため、働き口がない者が路頭に迷っているときに誰かが肩を叩きます。そのとき、その人が最低限の食事や住まいを用意してくれると囁いたらついていく者もあるでしょう。しかし、どんなに働いても自立できるだけの対価を与えられないとすれば、その生活はやがて泥沼にはまっていき、いわゆるタコ部屋生活に行き着きます。「まるで強制収容所のよう」と形容されるのがタコ部屋です。それを警察や行政が黙認していれば、そこから逃れる手段は路上生活しかありません。
ここに、タコ部屋生活と路上生活を2つの極としながら、そのあいだに大量のドヤ生活者という類型があるといった、山谷の典型的な生活様式のパターンが見出せるはずです。
だからこそ、のちに急進化した山谷争議団の直接の敵は、ゼネコンそのものというよりも、ゼネコンの需要を満たすべく暗躍している暴力団ということになるわけです。
ですが、いわゆる山谷暴動の最盛期に主要な敵と目されたのは警察でした。警察は狩り込みによって圧迫を加えてくるだけでなく、暴力団の活動を黙認し、時に暴力団への取り締まり以上に日雇い労働者や路上生活者に対して過酷に振舞うように見えました。
そうした場合、あたかも警察と暴力団とがグルに見えるということがあったでしょう。実際、そうしたスキャンダルがあとになって発覚したので、「ヤツらはグルだ」という見方はますます説得力を持ったりしました。
それだけでなく、ドヤというのは日雇い労働者が自立してしまえば経営に困るわけだし、そもそも暴力団の息のかかった旅館だって多いのだから旅館組合だってグルだろう…、さらに、俺たちにメシを高く売りつける食堂もグルに違いない…、俺たちを放り込む先の精神病院だって同じだろう…。
したがって、われわれ山谷の労働者の不条理な状況はこうした「構造」によってもたらされたのだ…、そう言われると少し違和感があるかも知れません。たしかに確固たる一枚岩の構造があってそれが日雇い労働者たちを一方的に抑圧しているというのは必ずしも正確ではない気がします。ただ、ゼネコンや暴力団やその他諸々が互いにもたれあいながら、それぞれに利益を引き出しあう緩やかな関係が存在したのはたしかに思えます。
包摂されざる人々に対して何重にも積み重なった寄生の構造があった、強い言い方をすれば最大の寄生者が戦後社会だったという言い方は成り立つのではないでしょうか。 |